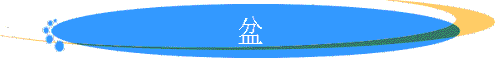お盆とは?
お盆は正式には「盂蘭盆会」と言います。
これはインドの言葉の一つ、サンスクリット語のウラバンナ(逆さ吊り)を漢字で音写したものです。
お盆のはじまりについて「盂蘭盆経」の中の親孝行の大切さを説いた教えが昔から知られています。
それは…
「お釈迦様の弟子の中で、神通力一番とされている目連尊者が、ある時神通力によって
亡き母が飢餓道に落ち逆さ吊りにされ苦しんでいると知りました。
そこで、どうしたら母親を救えるのか、お釈迦様に相談にいきました。
するとお釈迦様は、『おまえが多くの人に施しをすれば母親は救われる』と言われました。
そこで目連尊者はお釈迦様の教えに従い、夏の修行期間のあける7月15日に
多くの層たちに飲食物をささげて供養したのです。
すると、その功徳によって母親は、極楽往生がとげられました。」
という話です。
それ以来(旧暦)7月15日は、父母や先祖に報恩感謝をささげ、供養をつむ重要な日となったのです。
日本各地で行われるお盆の行事は、各地の風習などが加わる、宗派による違い、などによって様々ですが、
一般的に先祖の霊が帰ってくると考えられています。
新盆とは?
亡くなられてから初めて迎えるお盆を『新盆(にいぼん)』、または『初盆(はつぼん)』といい、
普通のお盆よりもお飾りやお供えを盛大にします。
親戚や故人と親しかった方々は、故人の成仏と感謝の心を込めてお供え物をします。
お盆提灯はお供えとして最高のものとされています。
新盆を迎えるご家庭では白い盆提灯を1個用意し、他に絵柄の入った盆提灯をお飾りします。
精浄無垢の白で霊を迎える意味から白木で作られた紋天が最も多く使われます。
軒先や縁側や仏壇の前に吊るして火を灯し、その灯りによって精霊に
迷うことなく家まで導かれるという意味が込められています。
新盆用提灯は1回(1年)限りです。
『新盆(にいぼん)』は地方によっては『新盆(あらぼん)』と言う処があります。
迎え火・送り火?
13日の黄昏に苧殻(オガラ)を門に焚いて亡き霊を迎えるのを「迎え火」といい、
16日にまた苧殻を焚くのを「送り火」といいます。
「魂迎え」・「魂送り」の意味です。
「迎え火」はお墓や玄関先で火を焚いて先祖が帰ってくる目印にするもの。
「送り火」は先祖を送り出す火ですが、ご家庭によっては実際に火を焚くことができない場合もあり、
そうした時には盆提灯に電気で明りを点すことや明りを入れないで
ただお飾りするだけで「迎え火」、「送り火」とすることもあります。
お盆の期間は?
お盆の期間は、東京などは7月ですが東北・関西やその他の地域ですと8月に行なわれます。
昔は陰暦の7月に行なわれておりましたが暦が太陽暦になった今日では
7月が新盆で8月が旧盆という慣習で地方によりそれぞれお盆の月が異なります。
迎え火は7月13日(8月13日)、送り火は7月16日(8月16日)ですが、
実際には7月(8月)に入ると同時に、盆提灯を仏前や玄関先・軒先に飾ります。
この期間、お仏壇を美しく飾り、果物や野菜、菓子などをお供えします。
僧侶を招いてお経を、あげてもらい、お墓参りをします。
お盆が終わったら…
新盆用の白い提灯は、1回(1年)限りの使用です。
新盆が終った時点で、お寺などに納めて【お焚きあげ】したり【川に流したり】します。
色の付いている『盆提灯』は毎年使えるものですから、
お盆が終わったら綺麗に拭いてから箱に入れて保管します。
|